[center] [/center]
[/center]
中学校の定期テストの点数がいまいち、成績が伸び悩んでいる子どもの将来を思うと、、、こんな不安をお持ちの保護者は多いと思います。
-
- そもそも家で勉強しない子
- 勉強してもできない子
勉強できない子は2つのパターンに分かれますが、共通する保護者の悩みのは「将来が不安」ということ。
親が代われるなら、代わってあげたいと一度は思ったことありませんか?
「一瞬で子どもが勉強できるようになる!」
そんな魔法はありません。
大事なのは、子どもの段階にあわせて対処すること(スモールステップの実践)です。
家で勉強しない子に関しては、以下のリンク先ページを先にご覧ください。
[kanren id=”456″]
家で勉強する習慣がついたら、次のステップに入りましょう。
学習習慣がついても、間違った考え方や学習法だと成績は上がりません。
「勉強してもできない子」の大半が、間違った努力をしています。
努力の仕方を学ぼう
保護者から子どもに一番伝えてほしいのは「努力すればいいってもんじゃない」ということ。
子どもは幼いころから「がんばろう」「やればできる」というメッセージを浴びせられています。
[center] [/center]
[/center]
「努力は大事!」と教わるわけですが、そのわりには具体的に努力の仕方を教えてくれる大人はいません。
[box class=”box23″]努力すれば夢は叶うと大人は言うけれど、それってどのぐらいの確率なの?[/box]
そんなふうに子どもは心のなかで思ってるのにもかかわらずです。
- 努力には方法論がある
- 努力した者が必ず報われるわけではないが、成功した人はみんな努力していた
この2点を子どもに伝えてほしいのです。
中国の古典「孫氏」のなかでも、自軍が不利な状況に根性論で勇敢に戦うことを愚行としています。
※孫氏の兵法は古くから日本の経営者やビジネスマンが愛読している書物です。
子どもが社会人になったらお祝いにプレゼントしてほしい1冊です。
成績をあげるためにやっていい努力、やっても報われない努力について解説します。
「勉強してもできない子」はいません
↑これは個別指導塾で15年間教え続けてきた経験から断言できます。
個別指導塾には、成績1から5まで、いろいろな子がやってきます。
「そんなこと言っても、事実、ウチの子はそうなのよ」と思うかもしれません。
でも、本当にいません。
「勉強してもできない」のではなく、「勉強してないからできない」のです。
子どもがウソをついてる(本当は遊んでる)と言いたいのではありません。
勉強だと思い込んでる行動を続けてるだけで、実際それは「勉強」だと呼べない
ということ。
テストで点をとるための行動が「勉強」。それ以外は勉強ではない
そもそも勉強する目的とはなんでしょうか?
ざっくりいえば「テストで目標点をとるため」ですよね。
じゃあ、子どもが今やってる「勉強」は、テストで点をとる「勉強」なのか?
ということです。
「今日は問題集を10ページやった」・・・これは勉強でしょうか?
「勉強した」といえるかもしれませんし、「勉強してない」といえるかもしれません。
例えば、数学の問題集を10ページやったとします。
丸付けしないで、ただ問題をやっただけ。
これは勉強といえるでしょうか?
言えませんね。
勉強の目的が「テストで点をとる」と定義するならば、できた、できてないかも分からない状態で、勉強したとは言えないはずです。
でも、実際、こういう子はとても多いのです。
やったことで満足してる、自分は勉強したのだと満足してる子です。
「勉強してもできない子」は、目的と手段をはきちがえてるケースがあります。
今話したのはほんの一例です。
自分ややってると思ってたけれども、「本当は勉強してなかった」と誰も教えてくれなかったのです。
まずは、「それって本当に勉強なの?」と考えてみる。これが”はじめの一歩”です。
[memo title=”Point”]”勉強してもできない子”はいない。
いるのは、”勉強してないからできない子”だけ
[/memo]
覚えたことを翌日に復習するのは効率が悪い
忘却曲線を用いて復習の重要性を説明されたことはありませんか?
100個覚えた単語は次の日にはこんなに忘れてるんですよ!
だから次の日に復習することが大事なんですよ!という感じで。
エビングハウスの忘却曲線の概要
- 20分後・・・58%
- 1時間後・・56%
- 1日後に・・74%
- 1週間後・・77%
- 1ヶ月後・・79%を忘れる
たしかに復習は大事です。
ただし内容によりけりです。
英単語を1000個覚えたいとしましょう。
1日10個ずつ覚えるとしましょう。
翌日は前日の復習をしてから次の単語にとりかかるようにスケジュールを組んだとしましょう。
たしかに悪くないプランかもしれません。
ただし高い確率で挫折するのではないでしょうか?
まず翌日に復習から始めることで、凹む子どもがでてきます。
覚えてないことに愕然とするわけです。
[box class=”box23″]昨日しっかり勉強したのに、、、半分しか覚えてない私ってバカじゃないの???[/box]
こんな感じで勉強のやる気がダウンします。
それよりなら復習ナシで1000個の単語を一巡することを優先すべきです。
1周するだけで自信がつきます!
復習のタイミングは、覚えた直後よりも後にしたほうが、長期記憶に残りやすいというデータもあります。
翌日復習する努力をやめて、単語帳やテキストを一周させることを目標にする。
テキストに愛着と根拠のない自信がわいてきます。
覚えてるかどうかを気にしなくて良いのです。
何周かすればいつか覚えるだろうという気持ちで十分。
単語の例でいうと、1日10個やるよりも、100個を10日で1周させるほうが良いです。
[memo title=”ポイント”]短期間で1周させる[/memo]
ちなみに「覚えよう」という気持ちで向き合うことは必要です。
結果を気にしないでという意味合いです。
まじめにやろうとする中学生ほど、テキストが途中でおわってしまいます。
意味のない努力ではなく、報われる可能性の高い努力をしてほしいと思います。
テスト週間だけ勉強しても高校入試で役立たない
[center]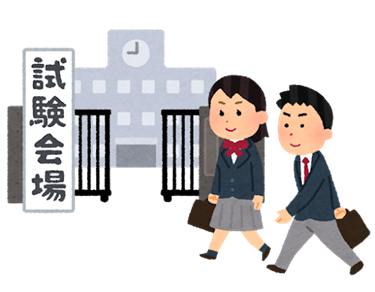 [/center]
[/center]
内申点は高いけれども、それに見合った点数が模試でとれない中学生が多いです。その理由はこれ。
定期テストのような出題範囲がハッキリしている場合は、短期集中で乗り切れます。
テストの点は良いのに、模試や学力テストでは点がとれない理由は、、、
[memo title=”ポイント”]短期間で覚えたものはすぐ忘れる[/memo]
高校入試のように範囲があるよう、ないテストには全然生かせずに終わります。
定期テストが近づくたびに自転車操業のように勉強し続けないと点数がとれず、受験勉強用にまた勉強しないといけないので二重の労力がかかります。
本来は3ヶ月を1ターンにして、テストに向けて受業の予習と復習を行い、テスト問題の間違えた部分を復習、長期休みに再復習をすれば、受験に対応できる力が備わるはずなのですが。
高校入試のような長期戦で範囲が膨大なテストに対しては、集中型よりも分散型の学習法が効果的であることは心理学の実験からも明らかにされています。
テスト範囲がでてから泣きながら勉強するのではなくて、定期テスト日に向けて日々の学習にはげむのが正しい努力の仕方です。
最近の子どもは損得や論理的な思考が優れているのに、付け焼き刃のテスト勉強が非合理的であることに気づけていません。
気づいているかもしれませんが、自制心が足りないせいか自分で修正できてないように見受けられます。
寝ないで勉強すれば何とかなるはウソ
[center]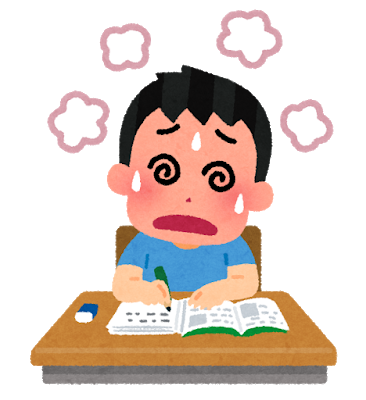 [/center]
[/center]
勉強してもできない子は、睡眠時間を削ってでも勉強しようとします。
これは間違いです。
寝ないでがんばれば何となると勘違いしてはいけません。
寝ないと脳の機能が低下して、よけいに勉強が進まなくなります。
仮にテスト前日に徹夜で勉強したとしても、頭が回らずテストを終えることになるでしょう。
社会科などの暗記系科目なら何とかなるかもしれませんが、数学はほど凡ミスを連発、本来であれば解けた問題まで失点するかもしれません。
体が弱い子どもはテスト中に気分を悪くして途中退席せざるをえなくなるかもしれません。
睡眠時間を削って得することは何もありません。努力の前に枠組みを決めてください。
つまり睡眠時間やお風呂に入る時間、食事の時間など絶対に必要な時間をさきに確保して残りの時間でどう動くかを決めるのです。
サラリーマンだと「おしりを決めろ」と上司から教わるやつです。
「時間=努力」と勘違いしてはいけない
勉強してもできない子は、何時間やったかにこだわります。
時間を意識しない努力は、ときに出来もしない壮大な夢、計画をたててしまいがちです。
1日24時間を全て勉強にあてることは不可能です。
あれもこれも勉強しようと学習スケジュールだけは立派で実行できなければ「絵に描いた餅」です。
[center] [/center]
[/center]
枠組みをハッキリさせるからこそ「優先順位を決めよう」「集中しないと」という発想がうまれます。
自分が勉強に1日に使える時間は3時間あるから、、、と枠組みを明確にするから、点数が伸びそうな社会科にこのぐらい、英語はこのぐらいという割当が決まります。
壮大な計画はたてないにしても、脳の集中力を意識したスケジュールをたててない子は多いです。
自分は1日に何時間集中できるのか?
これを子どもに考えさせてみてください。
「10時間はもつよ」なんて答えるでしょうか。
1日に最も集中できるのは3~4時間が限度です。
この制限時間内に何を勉強すべきかを意識して計画をたてさせてください。
もちろん学校が休みの土日や夏&冬休みであれば1日10時間を勉強にとることは難しくありません。
午前中に3時間、お昼から夕方までに4時間、夜に3時間ならギリギリとれます。
1日10時間勉強することは素晴らしいです。しかし「勉強時間が長い=努力している」と勘違いさせないでください。
時間が長ければ良いわけではありません。
仮に1日10時間の学習プランをたてるなら、最も集中できる最初の3時間(午前)に、何を勉強しようかと意識が向くように考えさせてほしいのです。
子どもが成長して社会人になったときに、「長時間労働=当たり前」と会社の洗脳にあわせないためにも親は教えなければなりません。今、世間では時間外労働の長時間化が問題になっていますよね。
時間をかけることは丁寧で素晴らしい、がんばっているという間違った考え方を持たないようにしないと、不幸な事件は自分の家族に及ぶかもしれません。
日常にながれる何気ないニュースが、自分の子どもにふりかかるかもしれない、、、自分ごととして考え、過労死や自殺など不幸の連鎖を断ち切る覚悟を持たないといけません。
[center] [/center]
[/center]
午前0時まで働かないと昇進できない会社は即やめさせるべきです。(大人ですから自分の意識でやめるべきですが)そんなこと言っても「転職なんて簡単にできないでしょ」と心配されるかもしれません。
だからこそ今勉強させないといけないわけです。再就職も余裕なほどの能力をつけさせる、子の将来を心配するなら教えるべきですよ。
もしかしたら保護者自身が長時間労働せざるをえない状況かもしれません。
ご自身、もしくはご家族を否定しない範囲で、新しい世代はそう行きないといけないんだよと伝えてください。
現状の社会では長時間労働※は当たり前の企業も多いし、家族を守るために働かないといけないという状況もあると思います。
「自分のことは棚に上げて言うけどね、、、」というスタンスでも良いと思います。
※関連資料
www.mhlw.go.jp
努力している自分に酔ってはいけない
大人にもいますよね?
努力している自分に酔ってはいけません。
「がんばっているオレ(もしくは私)ってスゴくない???」
みたいな感じでアピール感がハンパない。
やってる本人は気づいてませんが、非常に周囲から浮いてしまうので注意してください。
子どもなら自分にしか損害はありません。
しかし大人になると周囲に迷惑をかけます。
本当は助けてほしいのに自分一人で抱え込んでしまう大人。
孤独に耐えながら努力する自分に酔ってるだけで、仕事は進んでなかったりします。
早い段階で上司に相談すればよかったのに、締め切りをすぎてから「自分には無理」と投げてしまう。
どこの会社にも必ず一人はいるのですが、もしそれが自分の子どもだったらどうしますか?
努力は美しいという間違った認識を持たせないように注意してください。
勉強も同じです。
頑張る自分に酔うだけのナルシストでは、努力してるのに報われない残念な結果になりかねません。
分かりにくい授業はきかなくていい!
[center]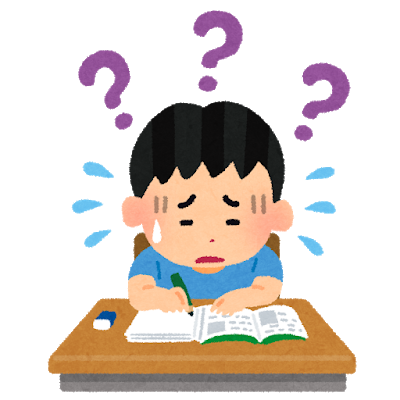 [/center]
[/center]
中学の授業は教師が主導権を握った閉鎖的な空間です。
説明の仕方が下手くそでも生徒はだまって受けなければなりません。
評価制をとりいれてる学校もありますが、ほんの一部。
日々研究しているならまだしも全ての人がそうとは限りません。
となると塾、講師の当たりハズレがでます。
説明が下手くそな授業を無理に聞く努力はいりません。
授業態度で評価が下げられないぐらいにキープすれば十分。
学校ばかりを悪くいえません。集団塾や個別指導塾だって同じ。分かりにくい講師だっています。
親がクレームを言いにいけば、さも子どもが悪いかのように対応してくる塾もあります。
もしくは自習に来てくださいと、拘束時間を長くすることで面倒見が良いことをアピールしてきます。
塾はお金をもらってるのですから結果をださないといけません。
親がクレームを言ってから対応する塾に通わせ続ける意味はあるのでしょうか?
ありませんよね。
勉強を教える教師(講師)との出会いはとても重要です。
残念ながら日本では質の高い教師を育成する環境にありません。
というのも「質」について抽象的であり議論されたことがないからです。
塾も同様です。
特に大学生が多いフランチャイズ展開してる個別指導塾では講師育成の研修はしていても、分かりやすい授業の仕方を具体的に教えるノウハウを持ってないところが多いです。
大きい塾ほど自社開発にこだわってるので、データを豊富にもっている教材会社との連携がありません。
しかも教務経験が全くない人が幹部になっているので手のつけようがありません。
マーケティングはプロなので販売戦略や商品パッケージの見栄えが良いのも、保護者が見破れない厄介なところです。
多くの個別指導塾は、指導方法の大枠は教えるけれどもあとは自分で何とかしてください、、、という感じです。
もちろん講師が経験を重ねて技を磨いていくのが本来あるべき姿ですが、大学生は数年でやめます。
3年務めてくれたらいいほうです。
本来なら大学生に頼るビジネス展開をするなら、10年選手のノウハウを短時間で身につけられるシステムを構築してないといけません。
講師の指導スキルよりも親がインターネットやパンフレットをみたときに「この塾いいわね」と反応してしまう箱物ばかりを本部は開発する塾が多いです。
こんなのあっても現場では役立たないんだよね~と嘆いている教室長は多く、各教室の努力で運営されてるところが非常に多いです。
分かりやすい授業を受けられそうな学習塾でさえ、よき師との出会いの確率は少ないのです。
子どもに正しい勉強法を教えるのが、よい講師という考え方もあるでしょう。
それだけなら高い塾代を払わなくてもネットや本で調べれば分かります。
もしくは塾で1ヶ月だけ勉強法を徹底的に押し込めば良いでしょう。
しかしそんな塾はありません。
すぐやめられたら商売になりません。
勉強方法を教えると声高に宣言しても、大きな矛盾を抱えこむことになるのです。
毎月の月謝を請求されます。
となると質の高い講師に出会えなければわりにあわないことになります。
お金に見合ったサービスを受ける権利があるのであり、「自習させます」「勉強法を教えます」という言い訳を聞く必要はないということ。我慢させて通わせてもお金の無駄です。
今は塾に行かなくてもインターネットで有名予備校や塾で活躍する講師の分かりやすい授業を受けられる時代です。
質の低い下手くそな授業に無理につきあう努力はいりません。それは無駄な努力です。
以上、「勉強してもできない子。残念な中学生にならないための努力論」という話でした。
コメント